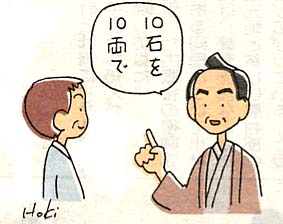最初に記号の交換だけを目的にした例を「先物(さきもの)」市場の成立から見てみましょう。
米の取引を例に取ります。初めのころの米の取引は、その年の秋に収穫された米を目の前に置いて競りが行われました。
ある日、松代藩の侍が言います。
「来年の暮れに、藩の殿様が結婚されるので、赤飯用のもち米が大量に必要だ。もち米が手に入らないと私の責任問題なので、誰か来年の秋のもち米を今から大量に売る約束をしてくれる者はいないか」
上越から来た庄屋が言います。「どのくらいの量が必要なのでしょう」
「10石だ」
「おいくらで買っていただけます?」
「10両でどうだ」
「それは良い値段です。早速、里に帰り、百姓衆に来年はもち米の耕作を多くするように頼んでみましょう」
こうして先物の予約が成立します。
先物市場の誕生です。
来年の米をいくらで、どのくらい買いたいとの希望を市場に予告する人がいれば、その情報に基づいて米の栽培を計画する人が出ます。
このことによって、来年の需要と供給が予測でき、作り過ぎの悲劇と、欲しい物が買えない悲劇がお互いに減少します。つまり、売る人と買う人の双方にメリットが出るのです。
先物相場は実際の米を目の前に置かないで、来年の米を頭の中でイメージして取引する作業です。ここから実物を取引する市場から、記号を取引する抽象的な市場が誕生していきました。
(2003年4月12日「長野市民新聞」)
 back お茶の間けいざい学 目次 next back お茶の間けいざい学 目次 next 
|