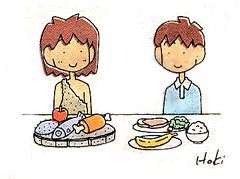|
別々の生活エリアで別々の生活スタイルを営んでいた家族が、互いに交流することで食料の融通ができ、飢えによって死ぬ可能性を大幅に減少できることに人類はすぐに気付きました。
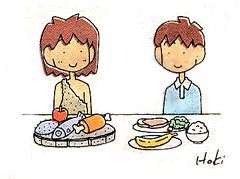
実は、交換経済の発見はもう一つ大きなメリットを相互の家族にもたらしました。
食料の組み合わせが豊かになったことです。
シカ肉ばかり食べていた家族、魚ばかり食べていた家族、芋ばかり食べていた家族。3つの家族の食卓には肉と魚と野菜が並ぶようになったのです。このことは当然に栄養バランスを改善させ、互いの家族の健康を増進させ、飢えの心配どころか長生きと健康維持への欲望を誕生させました。
食料の確保への動機だけでなく、豊かでおいしい食卓、健康に良い食材の組み合わせを求めて、人々はもっと広く交流するようになります。
経済活動の拡大です。
経済はより広い分野、より異質な分野と交流することで、財の組み合わせが多様になり、より大量の食料の保存と、より多様な食材の組み合わせが可能になります。それに気付いた人々は、交換そのものを目的にして広い地域を動き回るようになったのです。
この時点で、純粋に経済目的の交流と行為が人類に誕生して、人々が経済活動を始めたことになります。
これは今でも繰り返されており、中国野菜の輸入で生鮮野菜の値段が低下したり、日本の米が不作のときにタイから米が輸入されたり、昔は高根の花だったバナナやマンゴーやパパイヤが日常の食卓に載ったりすることとまったく同じ理由と行動です。
その意味で石器時代の発見は21世紀の今でも立派に生きています。
(2002年9月28日「長野市民新聞」)
 back お茶の間けいざい学 目次 next back お茶の間けいざい学 目次 next 
|