| お茶の間 けいざい学 (65) |
| 平等か競争か──世界で「対立」生む |
|
稲作文化の誕生は、集落のみんなが家族のように共同で働き、共同で食事をするのが良いとする全体を優先する考え方と、一枚一枚の田を個人所有にして、努力した人間の田から上がる収穫は、その人間の取り分にすべきであるという個人の能力に重きを置く考え方との対立を生みました。 |
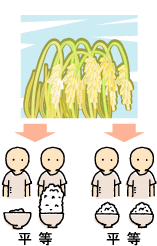 Hoki Hoki |
|
この全体主義と個人主義の対立は、経済思想だけでなく、その後の社会の政治形態や人の生き方をめぐる大きな対立点の始まりだったといえます。 |