稲作を中心とした社会では水争いを仲裁する人が必要で、これらの人々から武士が生まれてきたのは自然な流れでしょう。
収穫された米を江戸や大阪に運ぶ人、米と交換の塩や魚、木綿や食器を運ぶ人も専門化したでしょうから、商業も独立した形態となったはずです。
田を耕すくわやすきを作る鍛治(かじ)屋さんや荷車を造る職人さんも、だんだんと専門化していったでしょうから、工業も独立した職業分野として確立したことでしょう。
これらの職業はそれぞれに、社会構造に変化をもたらすスピードが違います。
まず、武士は社会のルールを作り守らせる役割ですので、社会変化への貢献度は低いでしょう。
農業も耕作方法の改良や種子の改良で収穫を増やすことはできますが、収穫量を一気に千倍にするような発明は生まれにくい分野です。
商業は異なった土地にある物を交換することで、それぞれの土地に住む人々のメリットを拡大させる仕事ですので、こちらも飛躍的に生産量を増大するというようなことが起こりにくい分野です。
最後が工業の分野です。荷車が発明されると、人が一つ運べた米俵を10個運べるようになります。現代のトレーラーでしたら、数百個単位、コンテナ船でしたら万単位でしょう。
工業分野の改良や発明は、生産性を千倍、万倍の単位で上げることが可能でした。近代の文明社会をリードしてきた産業が工業に見えるのは当然であり、近代は工業の発展から生まれました。
(2003年12月13日「長野市民新聞」より」)
 back お茶の間けいざい学
目次 next
back お茶の間けいざい学
目次 next 
|
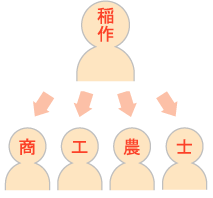 Hoki
Hoki