|
ローマ時代の一般の奴隷は主人の家にいて雑用をしました。知識奴隷も住込みの医者や弁護士、秘書のような仕事で、時間を決めて働くようなものではありませんでした。
日本の農民や中世ヨーロッパの農奴も土地に縛り付けられていましたが、働く時間まで決められていたわけではありません。
働く場所と時間、作業や動作の内容まで細かく決められたのは米国南部に連れてこられて、綿花農園で働かされた奴隷が最初でしょう。
現代のサラリーマンも、鎖の代わりに給料に縛られていると考えると、何だか悲しくなりますね。
このような労働の型が生まれたのは物を作る一連の過程が、綿花を摘む、糸を紡ぐ、布を織るなどの作業に分解され、効率化が図られたためです。
この作業の分解を誘導したのは、一か所の工場で同時に1000台の織機を動かして、効率良く大量生産を行おうとする発想が生まれたからです。
後にヘンリー・フォードがT型フォードをベルトコンベアーに乗せて生産する方式を考え出し、これがマスプロダクション(大量生産方式)と呼ばれるようになりました。
現代の大部分の人々の勤務形態を決めたのは産業革命が生んだマスプロダクションだったのです。
一か所に人を集中させ、同じ時間帯に働かせる方式は、大量の人々を工場や都市に移動させました。
地方から農村から集まった人々は自分の労働しか売るものがないので、労働者階級または無産階級とも呼ばれました。
新たな都市問題、過疎と過密、階級間格差などのさまざまな問題がここから始まりました。
(2004年4月3日「長野市民新聞」より」)
 back お茶の間けいざい学
目次 next
back お茶の間けいざい学
目次 next

|
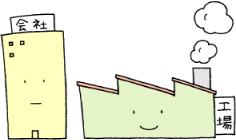 Hoki
Hoki